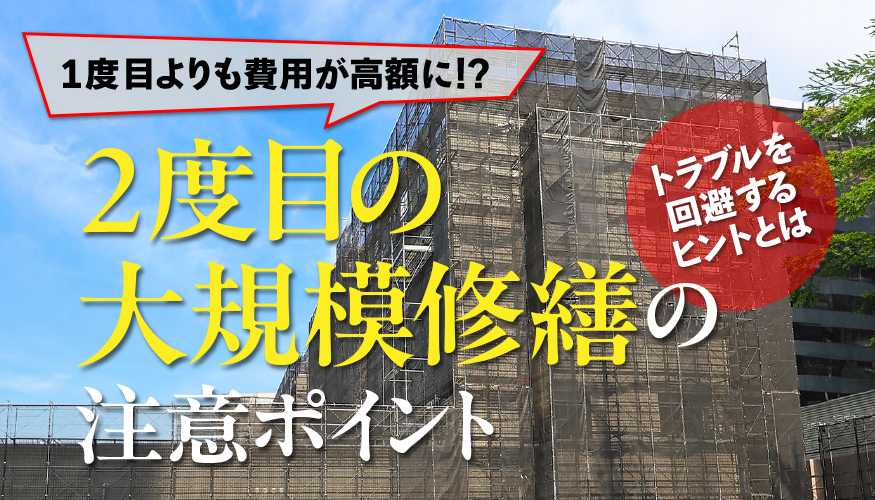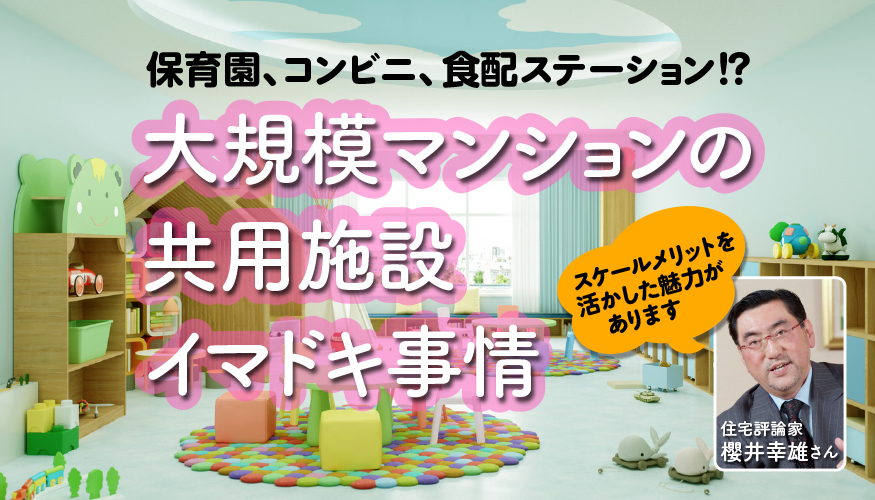共用廊下の構造が費用を左右する
2回目の大規模修繕工事では、防水や外壁などの「建築」、給水・排水をはじめとした「設備」が対象となります。具体的な内容や費用はマンションごとに異なりますが、費用に大きく影響するのは「共用廊下」の構造です。
例えば、タワマンによく見られる内廊下型の建物は、外廊下型の建物に比べると修繕費がかなり高額になります。というのも、廊下に関わる修繕の多くを、外廊下型では1回目ですでに実施していることが多いためです。
さらに内廊下型の場合、共用廊下の空調などの設備、内装の修繕が加わります。建物規模も大きい場合が多く、外廊下型に比べて費用が高くなることを覚えておきましょう。
一方、外廊下型の場合、玄関ドアが紫外線や雨風の影響によって劣化することがあるので、状況によっては、2回目の大規模修繕での対応を検討する必要があります。
考慮すべきは「耐久性」と「周期」
近年の修繕工事で考慮すべきは、資材の「耐久性」の高さです。例えば屋上防水の保証は10年というのが常識でしたが、今では15〜30年まで保証されるものがあります。同じく、サッシ周りのシーリングや外壁の塗料にも、長く安全に使えるものが出てきました。
大規模修繕工事はそもそも高額なうえ、昨今の物価高騰とともに工事費も上昇しています。こうした現状に対して、効果的かつ合理的に対応する手段のひとつとして、耐久性を高め、修繕工事の周期を延ばすことも視野に入れてみてください。周期を延ばすことで、60年間程度の長期間にわたる視点で捉えた場合、大規模修繕工事の実施回数を減らすことができるため、修繕積立金の負担額を一定程度削減することが可能になります。
ただし、周期を延ばすことによるリスクも忘れてはいけません。いくら資材の耐久性が向上したとはいえ、漏水や壁面のひび割れの可能性がゼロになるわけではありません。修繕周期が長くなるといっても、次の工事まで何もしなくてよいということではないのです。例えば16~18年周期で計画する場合であれば、5~6年目ごと、または8~9年目ごとに劣化の進行状況を確認して、劣化が見られた部分について補修を行うための点検と部分補修の予算を、長期修繕計画に折り込んでおくことが望まれます。

時代とともに求められる利便性も変わる
時代とともに人々の意識が変わり、新たな相談も増えました。1回目とは違う対応を迫られることもあるでしょう。
特に防犯面は重要視され、そのひとつが足場の変化です。工事期間中、常時建物の周囲に組まれる「鋼製の足場」から、1フロア分の作業スペースを上下させることができる「昇降足場」が使用されることも多くなっています。防犯性は高まりますが、工期が長くなり、費用が割高になるので、その点を加味しましょう。意外かもしれませんが、足場にかかる費用は全工事費の15〜20%、タワマンともなると30%以上にも及ぶケースもあります。
新築時から30年近くが経てばライフスタイルやニーズは変化し、求められる利便性も変わります。最近、相談が増えている宅配ロッカーの増設などはその一例でしょう。他にもエントランスの扉を自動にしたり、廊下を足音が響きにくい素材に変えたり、幹線道路沿いなどで共用廊下が騒音の影響を受ける場合などは、インターホンをノイズキャンセラー付きにしたりと、新たな需要が出てくるものです。
エレベーターと機械式駐車場は修繕できないケースも
一方で「修繕できない」ケースもあります。2回目の大規模修繕では、エレベーターや機械式駐車場などが対象に入ってきますが、部品の製造が終了していることがほとんどで、まるごと入れ替える必要が出てきます。エレベーターは1基あたり2000万円前後、タワマンでは億単位になることがありますし、機械式駐車場はシンプルなものでも1パレットで100万円を超えます。
駐車場の交換費用に関しては、管理組合内で賛否が対立するケースもあります。駐車場を利用していない住民が大きな負担を拒むこともあるからです。こうした軋轢をなるべく減らすためにも、毎月の駐車場使用料から定期的なメンテナンスや修繕、交換工事の費用などを、あらかじめ「修繕積立金」として積み立てておくことが大切です。

人件費や資材の高騰…経済情勢を見越した計画を
これまでお話ししてきたように、2回目の大規模修繕の際に問題となりやすいのは費用面です。「建築」部分と「設備」面の修繕・交換が重なりますので、高額になります。私が見てきた中には、もともとの計画の5割増から2倍以上に増額されたケースもありました。
修繕費不足のトラブルを避けるには、1回目の大規模修繕工事を終えた時点で、2回目だけでなく、3回目までを見越した長期的なスパンで予算を考えることが大切です。大きな見直しは国土交通省が推奨するように5〜7年ごとで構いませんが、物価高騰が著しい時期などは、単価については3年単位程度で見直すことが望まれます。建物や設備に支障が生じた際、資金がないからといって「修繕しないで放置する」という選択肢はありません。緊急性を伴う恐れがある場合には、借り入れるか一時金でしのぐしか方法はありません。
近年、人手不足による人件費や資材の高騰で、急激に修繕費は上がっています。長期修繕計画で費用をシミュレーションする際には、物価上昇率を見込んでください。正確な数値を定めるのは難しいかもしれませんが、経済・社会背景が少なからず影響することを念頭に考慮していただきたいと思います。
またトラブルを避け、うまく大規模修繕を進めるには、住民との合意形成も大切です。私が見ている中でも、住民の関係性が良好な管理組合では、スムーズに合意形成されるという印象です。良い関係を築き、良好な管理組合運営が、次世代の後継者に(事業)承継されていけるといいでしょう。
- 本記事の内容は2025年5月掲載時の情報となります。情報が更新される場合もありますので、あらかじめご了承ください。
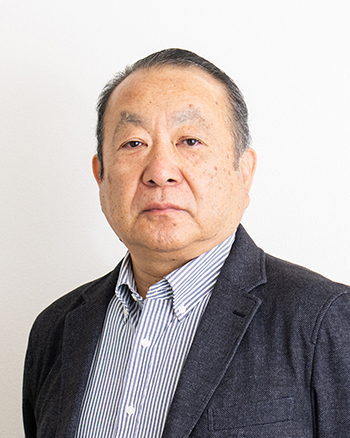
お話を聞いたのは●土屋輝之さん
つちや・てるゆき/さくら事務所マンション管理コンサルタント。2003年にさくら事務所に参画し、不動産売買および運用コンサルティング、マンション管理組合の運営コンサルティングなどを経験。不動産、建築関連資格を多数保有し、深い知識と経験を織り込んだコンサルティングで多くのマンション管理組合から支持を受けている。
https://www.sakurajimusyo.com/