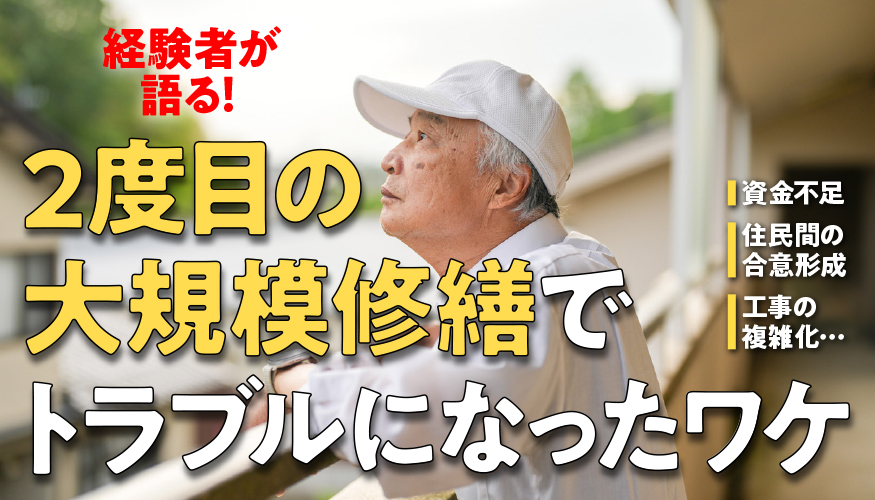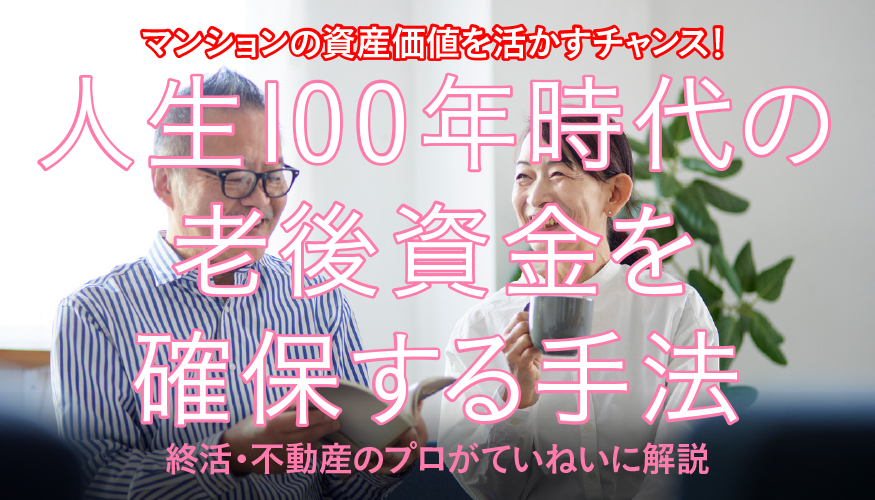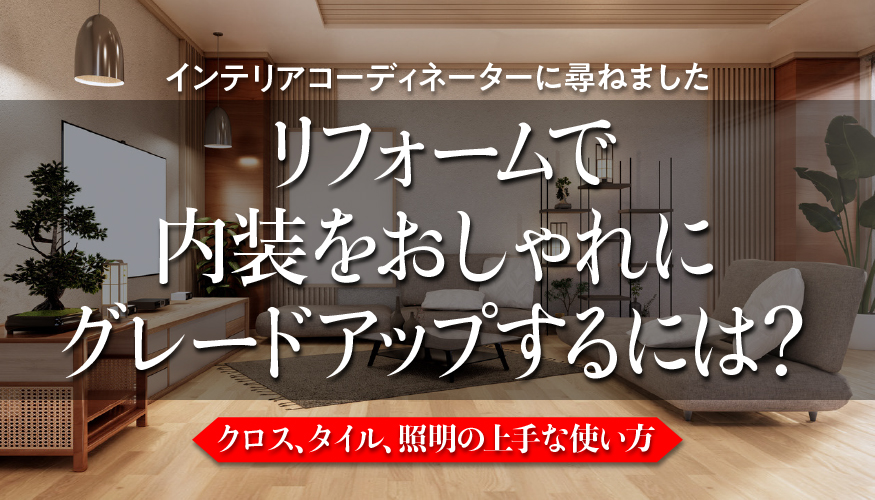まさか!? 世間を震撼させた「住民なりすまし」事件
マンションの大規模修繕は、一般的に12~15年程度の周期で行われます。2回目は1回目よりも修繕箇所が増え、工事内容も大掛かりになることが多く、費用が高額になる傾向があります。また、大規模修繕はマンションの住民(区分所有者)で構成される管理組合が主体となって実施するため、住民同士の話し合いによって工事内容や費用に関する合意形成が求められます。
2025年5月、首都圏のあるマンションで前代未聞の事件が起きました。大規模修繕工事の専門業者Aの社員が、住民から名義を借りて本人になりすまし、大規模修繕委員会に参加していたことが発覚。会議で業者の選定を誘導しようとした疑惑がもたれています。
このようななりすましのほかにも、工事会社の談合や理事長の独断など、大規模修繕工事に関するトラブルは少なからず発生しています。大きな金額が動くため、第三者の専門家の活用など、細心の注意を払って進める必要があります。
経験者が告白! 2度目の大規模修繕のトラブル事例
大規模修繕のトラブルを回避するには、実際に経験した人のエピソードが参考になります。そこで今回、レジクラ編集部は独自アンケートを実施し、具体的なトラブル事例を調査しました。
「工事が複雑になり、工期が予定より3カ月も延びた。工費も見積額を大きく上回り請求されたが、予備費として準備した金額以上は出せないと交渉。なんとかその範囲内で収まった」(77歳・女性)
「2回目の修繕費が積立金を上回ったため、すべての家庭に追加負担をお願いした」(56歳・女性)
「業者選定に時間がかかり、修繕費が高騰して工期が遅れた」(62歳・男性)
「理事会が素人すぎて専門知識がなく、まったく機能していなかった」(39歳・男性)
「立体駐車場の防錆施工がずさんで、施工後1カ月もたたないうちに錆が出てきた」(67歳・女性)
「都の補助金の入金遅れにより、工事会社への支払資金が一時的にショート。臨時総会を開き、第三者からつなぎ融資を受けた」(78歳・男性)
「新規入居者が理事を自ら引き受け、大規模修繕時に理事長にも就任。その後、理事会や総会の承認を得ずに知人の企業に工事発注の内示を行い、多額の金銭を受け取って発注しようとした。このため理事長を解任する正常化委員会を立ち上げたところ、委員会メンバーに対し不当な訴訟を起こすとともに警察等へ通報し、激しい争議に発展。最終的に解任に成功したが、その後も民事訴訟が続き、解決までに最高裁まで争う事態となった」(78歳・男性)

これだけは伝えたい! トラブルを避けるためのアドバイス
これから2度目の大規模修繕を迎える方に向けて、後悔しないためのアドバイスをご紹介します。
「修繕積立金が不足していないか、理事会の議事録などで常にチェックすべき」(45歳・男性)
「やる気のない管理会社の担当者は、会社に申し出て即刻交代させたほうがよい」(56歳・男性)
「修繕費は年々引き上げていくほうがよい。適時に積立金を増額しないと、一気に値上げしなければならなくなる」(69歳・男性)
「最近、大規模修繕工事を扱う会社間で談合が行われているとの報道もあった。管理会社が関与するケースもあるという。業者選定が何より重要」(78歳・男性)
「住民の中にも専門家はいるので、しっかりとした大規模修繕委員会をつくり、業者の言いなりにならずに交渉すること」(77歳・女性)
「工事業者のスケジュールをきちんと確認したうえで選定すべき」(29歳・女性)
「勝手に『大規模修繕委員会』を立ち上げ、理事長を兼任。『大規模改修が終わるまでは続ける』として7年近く居座った人物がいた。自身の思惑通りに進めるためだったようだ。理事会は面倒なこともあるが、一人に任せず、住民全員が意見を出し合い、“事なかれ主義”を排することが、最終的には資産価値の維持につながると思う」(60歳・男性)
いかがでしたか。経験者ならではのリアルな声を多数お寄せいただきました。ぜひ今回のアンケート結果を、今後の参考としてご活用いただければ幸いです。
- 本記事の内容は2025年8月掲載時の情報となります。情報が更新される場合もありますので、あらかじめご了承ください。