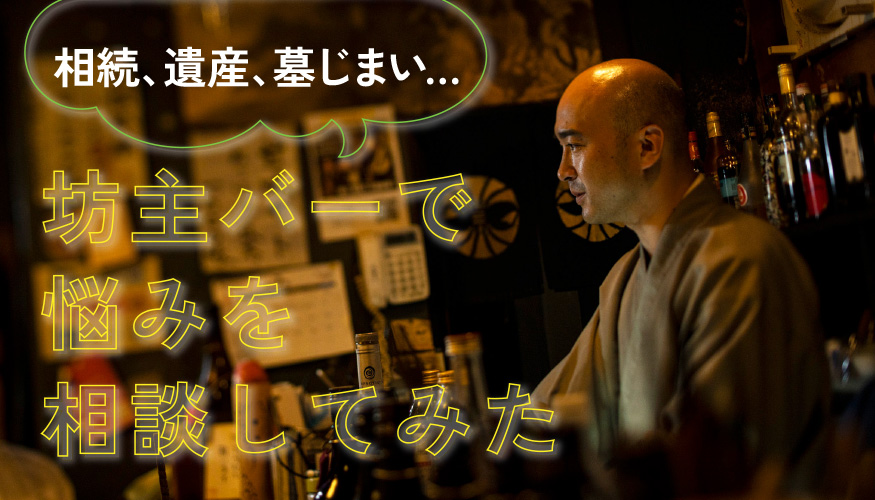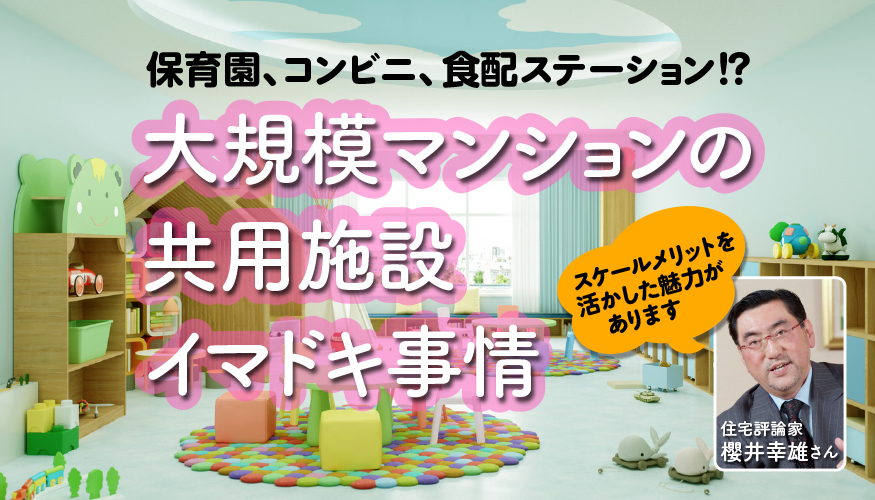その扉を開けると、仏教一色の異空間へ
「坊主バー」という店名を聞いたことがあるだろうか。その名の通り、現職の僧侶がカウンターに立ち、カクテルをつくり、接客をしてくれる酒場である。場所は、東京の荒木町。東京メトロ丸ノ内線の「四谷三丁目」駅から徒歩3分ほどの場所に位置する、焼鳥や鮨、小料理と風情ある飲食店が立ち並ぶエリアだ。この一画で異彩を放つのが、坊主バーである。
「檀家制」と書かれた扉を開くと、天井一面に写経が張り巡らされ、店の片隅には仏壇まであり、まるで異空間に飛び込んだよう。日常から切り離された気分になるせいか、カウンターに座るそばから、人に言えない悩みを打ち明けたくなってくる。



まずは名物のオリジナルカクテルを
お金にまつわる悩みは、なかなか人に相談しにくいもの。しかも遺産相続など生々しい話題は、親しい友人にだって詳細は話しにくい。ここは一つ、店主であり、浄土真宗本願寺派の僧侶である藤岡善信さんに、どうしたら遺産相続の悩みから救われるのか相談してみようか。いや、その前に、まずは飲み物だ。メニューを開いて目についたのは、「極楽浄土」という名のカクテル。
「極楽浄土には青と赤と黄色、そして白の4種類の蓮の花が咲いていると言われています。その光景をイメージした3層のカクテルです。ヒプノティックというトロピカルフルーツの味わいの青いリキュールや、マンゴーリキュールを使っているので、南国の果実のような味わいを感じられます」(藤岡さん)


遺産相続の揉め事から救われるには
坊主バーのオープンは2000年9月。藤岡さんは開店当初からカウンターに立ち続けてきた。昼間は僧侶として法事や葬儀へ行き、夜になれば坊主バーに顔を出す。まったく別の仕事のようだが、布教活動という意味では、藤岡さんのなかで二つはつながっている。
「仏教の教えを広く人々に伝えたいという気持ちは常に同じです。坊主バーでも、毎日21時と22時半に1回ずつ、お客様と法要を行います。強いて言うなら、昼と夜とではアプローチが変わる。葬式や法事は亡くなった人へ向けて行うので、死に寄せたお話になります。坊主バーでは、訪れる方々に向けて生き方に焦点を当ててお話ししていくからです。といっても、浄土真宗の教えはすべて『南無阿弥陀仏』へとつながっていきますから、私が話していることは一貫して同じです」
実は筆者に小さな悩みがある。10年ほど前に母親が再婚したのだが、その相手には子どもがいる。いつか訪れるであろう遺産相続のタイミングで、何かしらの揉め事が起きないか心配なのだ。どんな心の準備をしておけば、遺産相続の揉め事から救われるのだろうか。
「『相続』とは、仏教でもよく使う言葉です。しかしそれはお金や不動産ではなく、仏の教えを指しています。宗派によっては『法統相続』と言ったりもしますが、浄土真宗でも、念仏を子や孫、あるいは弟子や生徒へ正確に伝えていく、という意味で『相続』という言葉をよく使います。そう考えると、現代における親から子への相続も、最終的にはしつけや道徳、生き方など、教えを伝えていくのが一番いいのでしょう。
以前、タイの僧侶からこんな話を聞いたことがあります。曰く、『一番良くない相続はお金』であると。なぜなら、お金は争いを起こすものだからです。災いの元となるものを相続するのは良くない。だから、どこかに寄付したりして、お金を残さない生き方をするべきだというのです。
先立つ人は、残していく人々への思いやりとしてお金を残そうとするものです。しかし、人間にはやはり煩悩がありますから、どうしたって争いが起きてしまう。すぐに手に入るお金があると思えば、ラクをしたくなる。ただ、親の教えをまず相続して、それを念頭に置けば、欲張る心は生まれてこないでしょう。そうすると、揉めずに美しく金銭を分け合うことができるのかもしれません」
何のためにお墓があるのか

もうひとつ、筆者には人には話しにくい悩みがある。父親が、死後は愛媛県の寺に建つお墓に埋葬してほしいというのだ。しかし筆者は生まれも育ちも、現在の住まいも東京。愛媛県に親戚がいるわけでもない。遠い先祖がたまたま愛媛に残してしまったお墓に埋葬してほしいと、父が言い張っているのである。
父の死後、一体、どうやって遠く離れた土地の墓を管理すればいいのか? お盆のたびに行き慣れない愛媛県へ足を運ぶのも、現実的な話ではない。父の死後、こっそり墓じまいしてしまおうかと考えているのだ。
「世代によってはお墓を守るという習慣をお持ちの方もいらっしゃいますが、近年は変わってきました。管理費が払えない、受け継ぐ人がいない、という理由で更地にして大供養されるケースもあります。
何のためにお墓があるのかというと、残された人の拠り所とするため。お釈迦さまのお墓も、後の人がお釈迦さまを思うために建てたものです。では当のお釈迦さまはどう考えていたかというと、諸行無常であり、骨というのは物質であって意味がないとおっしゃっていたようです。親鸞聖人も同じ。肉体には意味がなく、生命の本質は仏の世界に行っても消えることがない。だから、亡くなった後は自分の肉体は鴨川に流して魚や鳥に食べさせてあげてほしい、と言い伝えていたそうです」
亡くなった後も、必ず出会える世界がある
藤岡さんの言葉で、「お墓を守らなければならない」というプレッシャーからは解放された。しかし、ふと思うのだ。お墓を失ったら、一体、どこで手を合わせればいいのか?
「たしかに、お墓は手合わせる場所であり、拠り所となるでしょう。ただ、お墓にこだわりすぎなくてもいい、という考え方もあります。親鸞聖人は、『南無阿弥陀仏』というお言葉だけを残し、念仏するところに私もいるとおっしゃっていたそうです。
それを現代に置き換えると、亡くなった方から受け継いだものを思い出すと、そこにその人がいることになる。例えば、『おばあちゃんがよく、靴は揃えなさい、と言っていたな』と玄関で思い出すとしますよね。すると、そこにおばあさんがいるのです。料理でもいい。母親がつくった煮物はこんな味だったなと考えて考えるとき、亡くなった方は常にそばにいるのです」
仏の教えに触れて、だんだん心が軽くなってきた。ところで、今から知っておきたいことがある。遺産相続よりも、墓じまいよりも、まず親を失ってしまったとき、私たちは別離の悲しみをどう乗り越えるべきか。最後に藤岡さんに聞いた。
「仏教では、亡くなって終わりではないと考えています。死とは、しばしのお別れであり、出会い直すきっかけです。生きているうちは親が鬱陶しいと思ったり、なかなか気付けないことがある。しかし、亡くなって1年、2年と時が経つうちに、ふと親のすごさに気付く瞬間が訪れることでしょう。そのときに、出会い直すのです。亡くなった後も必ず出会える世界があると思うことが、安心につながるのではないでしょうか」
取材・文●吉田彩乃 撮影●オカダタカオ(2024年8月掲載)
- 本記事の内容は掲載時の情報となります。情報が更新される場合もありますので、あらかじめご了承ください。