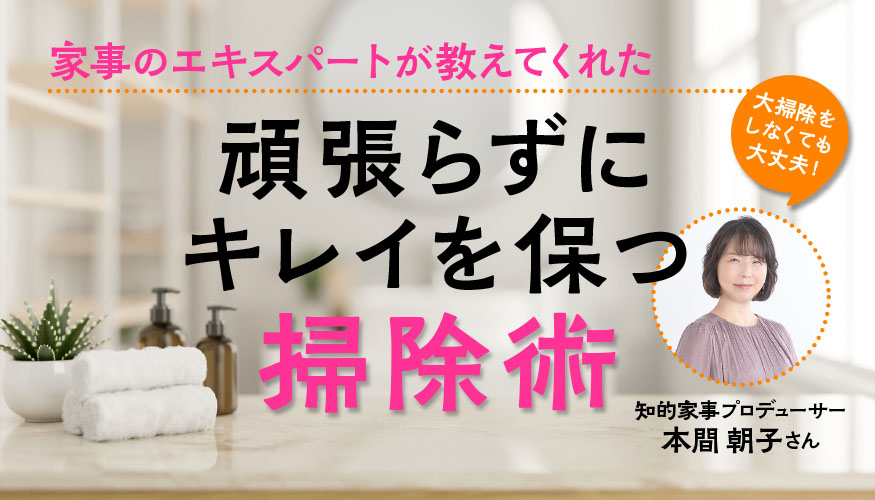大きな汚れになる前に!予防掃除の4つの考え方
実は「家事の中でも特に掃除が苦手」だった本間さんが 「予防掃除」を思いついたのは約10年前。ラクな掃除法の情報はあったが「そもそも掃除をせずに済ませる方法はないか」と考えたのだ。きっかけは意外な分野だった。
「当時『予防医療』という言葉をよく耳にしました。病気になってから治療するのではなく、そうならないよう事前に対策するものです。これを家事に活かしたらどうだろうと。つまり、汚れが付いてしまう前に落としてしまえば掃除を頑張らなくて済むのではないか、と思ったんです」
本間さんの考える「予防掃除」は大きく4つに分けられる。
●「汚れるもの」を使わない
掃除が必要となるものを極力使用しないことで、汚れの機会を減らす考えだ。
「キッチンマットや三角コーナー、歯ブラシスタンド、シャンプー棚、排水口カバーなどです。ものを置く分、汚れや掃除の対象が増えてしまいます。便利グッズや使い捨てタイプに切り替えるといいでしょう」
●表面を事前にカバーする
物の表面に汚れがつかないよう予防するだけで、掃除の手間はグッと減る。
「私は、油はねガードを使ってコンロ周りを防いでいますが、実はグッズを買わず、身近なものでカバーできる場所もあるんです。例えば、冷蔵庫の調味料置き場にはキッチンペーパーを敷く、ホコリが溜まりやすい洗濯機の排水ホースにラップを巻くなどで十分。細かくて掃除しにくいサッシの溝や、トイレと床の間の隙間にはマスキングテープを貼っておくと便利です」
●汚れに強いアイテムを選ぶ
抗菌機能のついたグッズを選ぶのも一手段。水回りでは、シャンプーや歯ブラシ収納を「吊るすタイプ」にするとカビやぬめりがつかず、掃除の手間を減らせる。
●たまりやすい場所をなくす
わずかなスペースなど「掃除しにくい隙間」があるとホコリはたまりがちだ。
「掃除機のヘッドやフローリングワイパーの幅に合わせて、家具と壁の隙間をあけておけば、ふだんの流れで掃除できます。観葉植物や空気清浄機など重いものはキャスター台に載せたり、テーブルや椅子の脚に滑りやすいカバーをつけたりすると、移動も簡単です」

よりラクになるコツ① 動線を見直せば「ついで」「ながら」でOK
日々の生活が忙しく、「予防掃除」すら面倒だという人は、まずは動線を見直そう。
考え方を変えれば掃除は「やろう!」と決めなくてもいつでもできる。生活動線に組み込めば、負担なく「いつの間にかきれいにする」ことも可能になる。
●手洗いの「ついで」に
家に帰って手を洗う際に、手についた石鹸の泡でそのまま洗面ボウルをなでるだけで清潔を保てる。
「水はミネラルを含んでいるので、乾いたときに水垢として目につきやすいもの。蛇口の水滴を拭き取るだけでもきれいに見えます」
●排水ネットを交換する「ついで」に
キッチンの排水口のネットを変えるときは、新しいネットをスポンジとして使用。食器用洗剤をつけて、サッとシンクを磨いたらそのままセットすればOKだ。
●お風呂に入り「ながら」
風呂から上がるときにシャワーで熱めの湯を壁にかけるだけでも、皮脂や石鹸のカスを流せるのでカビ予防に。
●朝起きてリビングに向かい「ながら」
ベッド脇にフローリングワイパーを置いておき、起きたら通る場所だけを拭きながら歩く。
「おそうじスリッパも有用です。このように、気がついたときにやっておくことが、のちの大きな掃除を避けるポイントになります」

よりラクになるコツ② 自分以外の力を借りる

自分以外の手を使うこと。便利なグッズや外部を頼ればより効率的に掃除はできる。
「最近は『置くだけ』『かけるだけ』など、労力をかけなくてもきれいにできる商品や、掃除が楽しくなるようなグッズがたくさんあるので、上手に活用してください。手が回らない箇所は、外部サービスに依頼するのもいいでしょう」
生成AIを活用するのもひとつ。やるべきことを入力して優先順位を聞けばリストにして出してくれ、スケジュールを考えるわずらわしい手間が省けるからだ。掃除は必ずしも一人でするものではない。たとえば「休日の午前を家族全員で掃除する時間にしたり、コツ①のような動線でできることを、気づいた人にやってもらう習慣をつけるといい」と本間さんはアドバイスする。
「掃除は、料理や洗濯とは違って先送りにできてしまうので、わざわざ時間を取りにくいかもしれません。一人で頑張らず、家族や外部サービスなどの外部を巻き込んでシェアしながら、日々の生活でしていきましょう。自分が苦と思わない方法で住まいの価値を保ってください」
- 本記事の内容は2025年3月掲載時の情報となります。情報が更新される場合もありますので、あらかじめご了承ください。

お話を聞いたのは●本間朝子さん(知的家事プロデューサー)
ほんま・あさこ/仕事と家事の両立に苦しんだ自身の経験から、家事の効率化メソッド「知的家事」を考案。雑誌、ラジオ・テレビなどのメディアのほか、講演活動などを通じて、家事の組み立て方を根本から見直す方法を提案している。著書に『写真でわかる!家事の手間を9割減らせる部屋づくり』、『60歳からの疲れない家事』(青春出版社)、『ムダ家事が消える生活』(サンクチュアリ出版)などがある。
https://honma-asako.com/