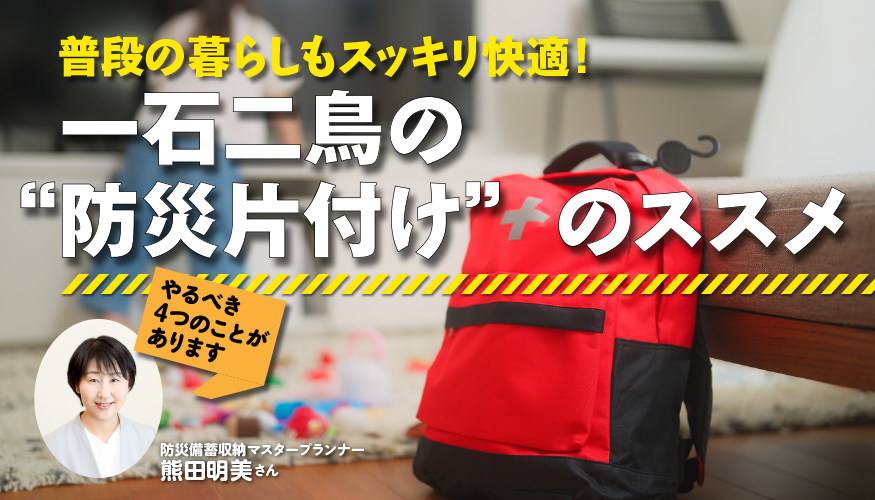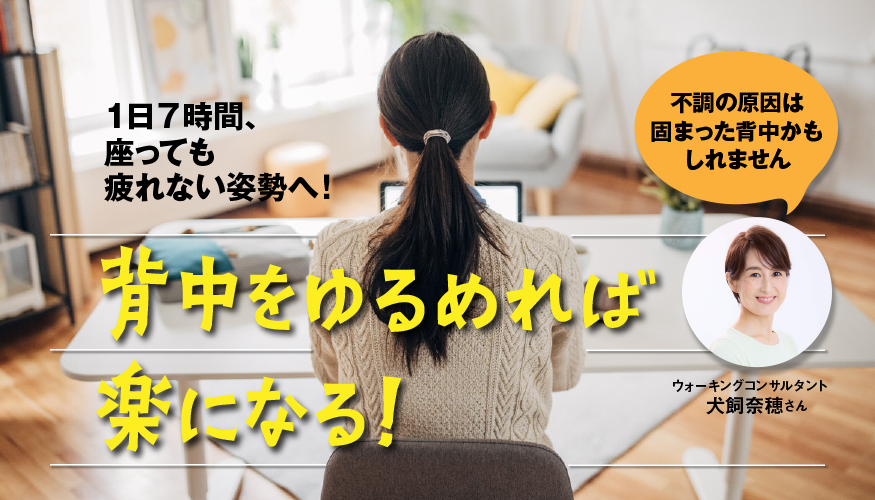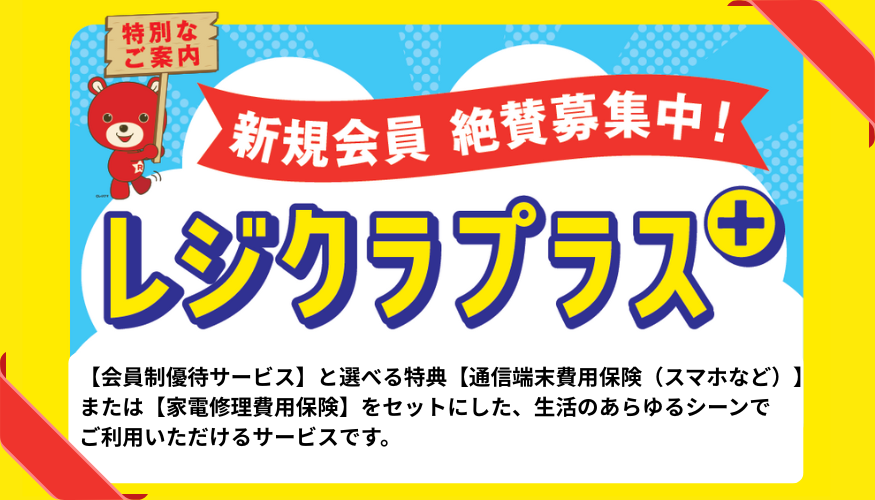なぜ、防災片付けが必要なのか?
地震や台風など自然災害の多い日本では、日頃から防災について考え、備えておくことが大切です。しかし、家の中にたくさんのモノがあふれ、防災グッズや食料などの備蓄を置く余裕がないというご家庭は少なくありません。
こうした状態の家で災害に直面した場合、避難する際にモノにつまずいて転んで怪我をしたり、家具がドアを塞いで家から出られなくなったりする可能性があります。また、災害で流通がストップすれば、食料や生活消耗品が手に入らず困ってしまうでしょう。
しかし、いざたくさんのモノを片付けようと思っても、目的があいまいだとスムーズに進みません。そこで意識したいのが“防災片付け”です。防災を意識して片付け、防災用の備蓄を収納するスペースをつくることで、日常生活は快適に、災害時もスムーズに対応することができます。
防災片付けでやるべき4つのこと
防災片付けでやるべきことは、【知る】【片付ける】【備蓄】【収納】の4つです。
①知る
まずは、住んでいる地域のハザードマップを見て、地形の特徴や起こりやすい災害について知りましょう。防災マップで避難所や災害時拠点病院の場所、避難ルートなども確認しておくこと。それを踏まえて、災害時に災害種別ごとにどういう行動を取るのかを家族で共有し、対応できる備えについても考えておくことが大切です。
②片付ける
災害が発生しても普段と変わらないような生活ができるように、家の中を見直して不必要なモノを処分し、食材や生活消耗品、防災グッズなどを備蓄するためのスペースをつくりましょう。さらに、「災害時に危険ではないか」という視点で家の中を見直し、モノの置き方やインテリアを考えます。例えば、以下のような対策をとることができます。
- 廊下や玄関は避難経路になるので、つまずきやすいモノやドアを塞ぐモノは置かない。
- 背の高い家具・家電はドアを塞がない向きに設置し、転倒防止対策をとる。
- 花瓶など割れやすいモノは、ジェルマットなどで落下防止対策をとるか、割れにくい素材に変える。
③備蓄
食料や生活消耗品といった防災備蓄は、家族全員で7日間ほど自宅避難できる量を目安に準備しましょう。以下のアイテムを参考にしていただき、各自が必要なモノは必ず追加します。
- 水(1人1日3ℓ×7日分×家族人数が目安)
- 自分や家族が好きな食べもの、防災用保存食
- 紙コップ、紙皿、割り箸
- カセットコンロ、カセットガス
- 日用消耗品、衛生品
- 非常用トイレ、トイレットペーパー
- 電源
- あかり
- ラジオ、イヤホン
- 連絡先一覧
- 小銭
- 非常用持ち出し袋
- ヘルメット(防災頭巾) など
そのほか、薬やメガネ、コンタクトレンズなど個別に必要なモノも忘れずに。災害時、ペットの物資は手に入りづらいので、多めに備蓄しておきたいところです。
最近は必要以上に防災グッズや備蓄を買い過ぎている方も多いですが、管理できないと結果的にモノが増えてしまうことになるので、収納場所を確保し適正量を把握することが大切です。
④収納
収納場所は家の構造などにより異なりますが、普段の生活に支障がなく、さらに災害時にすぐに取り出せる場所に用意した備蓄アイテムを収納します。2階建て以上の場合は、1階だけにまとめるのではなく、各階に収納し、どこに何があるのかを家族で共有し、災害時に家にいる人が分かるようにしておいてください。

“ローリングストック”を活用して効率的に備蓄しよう
食材の備蓄は“ローリングストック”を活用するのがおすすめです。ローリングストックとは、日常生活で食べるもの、かつ災害時にも食べられるものをストックしておき、食べたら買い足すようにすることで、効率的に管理する方法です。
ローリングストックをする際に意識してほしいのが、最低在庫数を決めておくこと。我が家の場合は、缶詰などの収納カゴにシールを貼って個数を管理。食べたら在庫数をチェックし、最低在庫数に達していたら買い出し係の私に報告するというルールを家族で共有しています。
どうしてもローリングストックでの管理が向いていないという場合は、「防災用」として販売されている長期保存のできる食材を備蓄しておきましょう。どんな形であっても、災害時に安心して食べられる備蓄がしっかりと用意しておけることが大切です。
(2024年3月12日掲載)

お話を聞いたのは●熊田 明美さん
くまだ・あけみ/「NiceLife」代表、防災備蓄収納マスタープランナー、防災士、整理収納アドバイザー。
2011年の東日本大震災をきっかけに防災と整理収納を学び始める。2017年に「NiceLife」を設立。現在は個人向けの整理収納サービスや防災アドバイスのほか、認定講座やセミナーの開催、講演活動、メディア出演・掲載など幅広く活躍中。
https://www.nicelife-sbs.com/