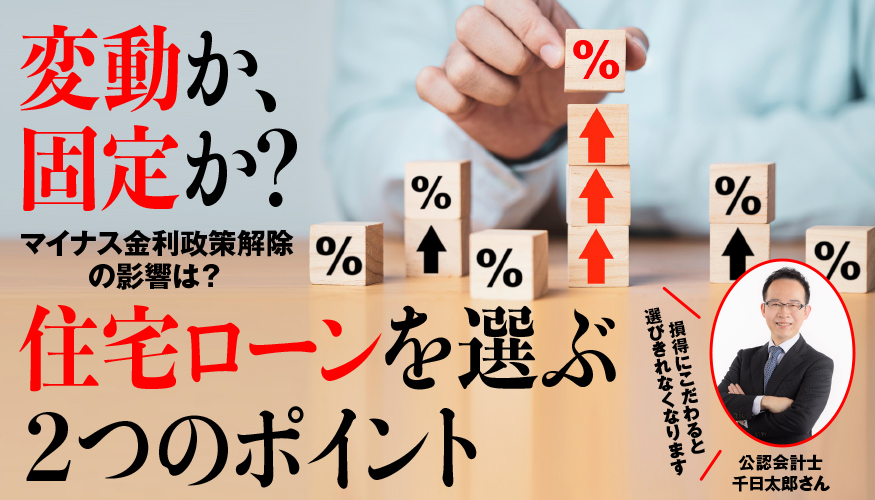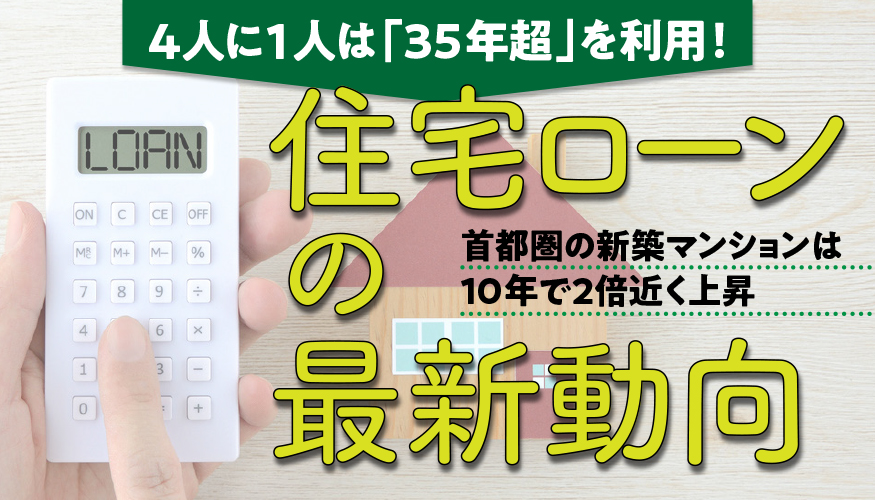マイナス金利政策解除が住宅ローンに与える影響
マイナス金利政策の解除による影響は、住宅ローンの種類によって異なります。
●民間金融機関の固定金利
今後金利が上がっていくことを見越し、固定金利を上げ始めている金融機関が出てきています。ただ、現状で年2%を超えて設定している金融機関はほとんどありません。
●フラット35(住宅金融支援機構の固定金利)
金利政策の変化に伴って金利を上げるといった動きは出ていません。子どもの人数によって金利が引き下げられる「子育てプラス」などの金利引下げ制度も充実しているので、利息の負担を抑えやすいといえます。
●変動金利
今後、金利が上がっていくことが予想されます。いつ上昇局面に入るか、どの程度上がるかといった詳細は明確にはわかりませんが、上がっていくことが前提となるでしょう。ちなみに、住信SBIネット銀行とイオン銀行は変動金利の基準金利を0.1%上げています。
民間金融機関では、固定金利・変動金利ともに上がっていく可能性があります。ただし、今すぐ大幅に上がるということにはならないでしょう。なぜかというと、大幅な金利の上昇に耐えうるほど好景気とはいえないからです。現在の日本の状況から考えると、金利が上がるとしても緩やかでしょう。
今後は金利の上昇を懸念して固定金利を選ぶ人が増えるかもしれませんが、固定金利と変動金利のどちらが得になるかは、実際に返済し終えるまでわからないものです。損得にこだわってしまうと、選び切れなくなるでしょう。
「固定金利」と「変動金利」を選ぶ2つのポイント
住宅ローンの金利を選ぶ際には、それぞれの特徴をきちんと把握することが大切です。
●固定金利
借り入れたときの金利が、全返済期間を通じて変わらないタイプ。フラット35も固定金利。借り入れ時点の金利は、変動金利より高い水準に設定されています。
●変動金利
金融情勢の変化に伴い、定期的に金利が変動するタイプ。金融機関の多くが、金利上昇後も5年間は直前の元利均等返済額を維持する「5年ルール」と、6年目からの返済額の上限を直前の125%までとする「125%ルール」を採用しています。
それぞれの特徴を踏まえたうえで、ポイントとなるのは「家の選び方・買い方」「ライフプラン」です。
ポイント1:家の選び方・買い方
いずれ住み替えることを前提にリセールバリュー(再販売する際の価値)を重視して家を選ぶ場合は、変動金利がマッチするといえます。金利を固定する期間が長ければ長いほど、金利は高くなりますので、その固定期間よりも早く完済するのであれば、そんなに長い期間にわたって金利を固定する必要はなかったということになるからです。
一方、こだわりの注文住宅に長く住む場合は、固定期間に設定した返済期間をフルに使って返済していくことが予想されるので、固定する期間に応じた高めの金利を払う代わりに、金融情勢の影響を受けず金利を固定できる固定金利が合っているでしょう。
ポイント2:ライフプラン
子どもを育てている夫婦、または今後子どもを持つ予定がある若い夫婦であれば、金利変動のリスクを負わない固定金利のほうが安心です。フラット35の「子育てプラス」を活用すると、当初の期間は金利を最大年1%引き下げられます。
逆に、すでに子どもが独立している家庭や子どもを持つ予定のない家庭は、経済的な余裕が生まれやすいので、変動金利でもいいかもしれません。ただし、将来的に金利が上がったら支払えないと感じるようであれば、固定金利も視野に入れましょう。
これだけは避けたい! 住宅ローンの借り方
変動金利で住宅ローンを組む場合は、今後金利が上昇する前提で返済計画を立てていきましょう。
住宅ローンを組む際に頭金をたくさん入れて、手元のお金がなくなってしまうといったリスクのある借り方は避けたいところです。
金利が上がった際にも返済し続けられるよう、余裕を持った返済計画が重要になります。月々の返済額を低く設定する、頭金を入れずにあえて手元の資金を残しておくといった対策が必要になります。
(2024年6月7日掲載)
- 本記事の内容は公開日時点の情報となります。情報が更新される場合もありますので、あらかじめご了承ください

お話を聞いたのは●千日太郎さん(公認会計士)
せんにち・たろう/オフィス千日合同会社代表社員。
大学卒業後、大阪の監査法人へ入社。資格や名前を伏せて始めた「千日のブログ 家と住宅ローンのはてな?に答える」が評判を呼び、住宅ローン、不動産分野で人気の高いコラムニストとなる。YouTubeでは、公認会計士としての金融商品の分析力と独自のノウハウをもとに、日々寄せられる読者からの相談に的確なアドバイスを行う。著書に『住宅破産』(MdN新書)、『住宅ローンで「絶対に損したくない人」が読む本』(日本実業出版社)など。
https://sennich.hatenablog.com/