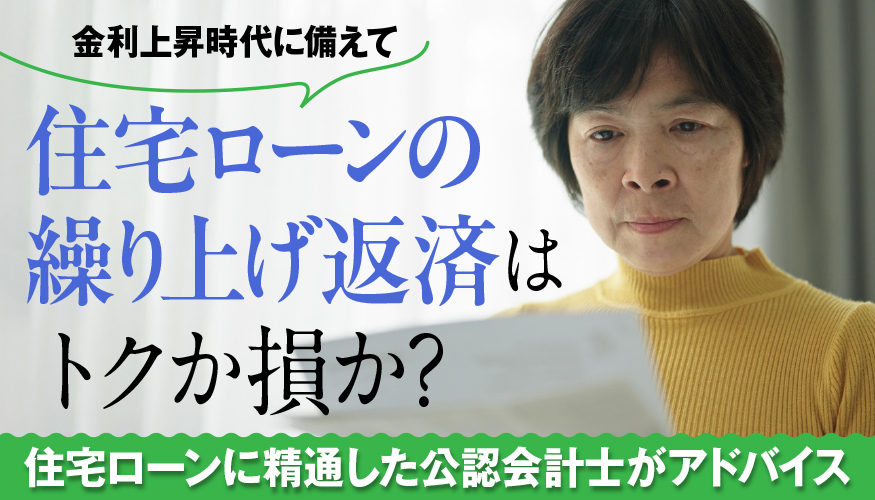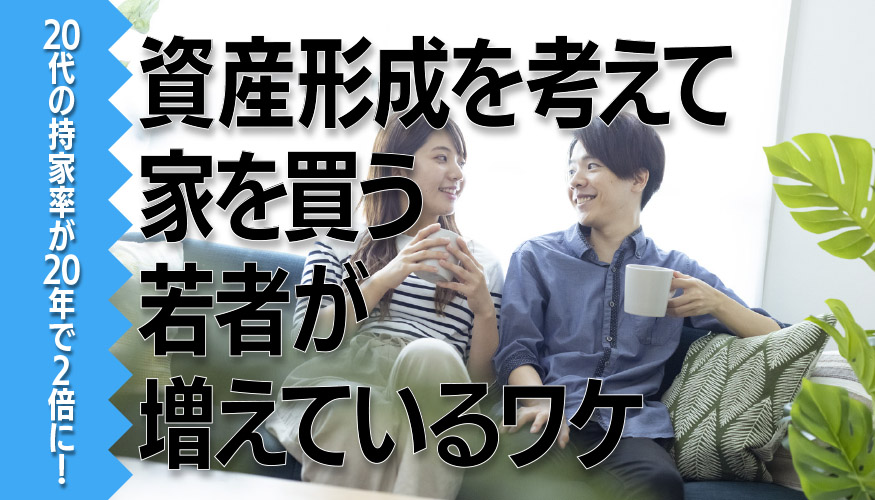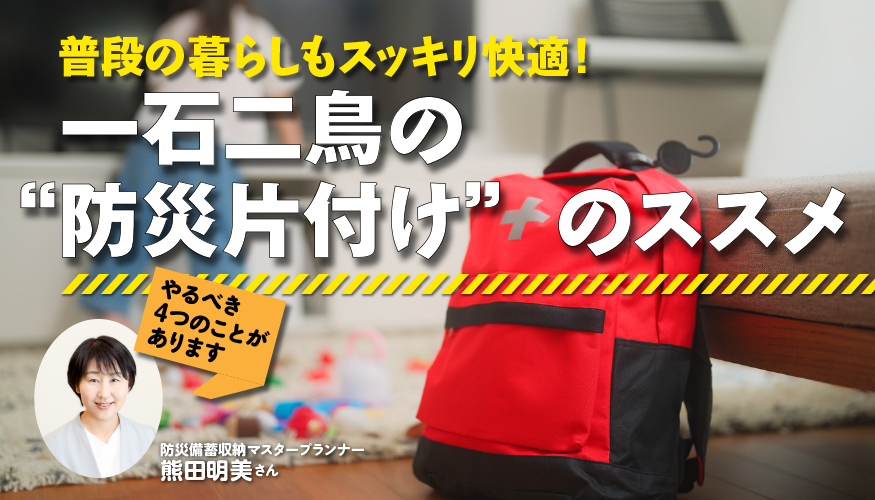繰り上げ返済のメリットとデメリット
まずは繰り上げ返済を行うメリットとデメリットを考えてみましょう。
メリットは「借金が減ること」と考えがちですが、その分手元に残る現金(預貯金)が減るので、厳密にはメリットとはいえません。確実にメリットといえることは、将来発生する利息を減らせる点です。
デメリットは、先に述べた通り、現金が減ること。現金は、病気やケガ、離職など、想定外のアクシデントが生じた際にすぐ引き出せる流動性の高い資産です。現金が減るということは、アクシデントに弱い財政状態になるということです。
また、住宅ローン控除が適用されている間に繰り上げ返済を行うと、住宅ローン残高が減るので、住宅ローン控除の効果が小さくなってしまうというデメリットも挙げられます。
いますぐ、繰り上げ返済を行うべき?
繰り上げ返済のメリットとして「将来発生する利息を減らすこと」を挙げましたが、そもそも住宅ローンはあらゆる金融商品の中でも極めて金利が低い商品です。加えて、住宅ローン控除によって利息負担がほとんどないことに鑑みると、繰り上げ返済のメリットは実感しづらいといえます。
ただ、現在は住宅ローン金利が上昇傾向にあるといわれているので、今後の上昇の度合いによっては、繰り上げ返済のメリットが大きくなる可能性もあります。特に変動金利が想定を超える上昇となった場合には、その効果が大きくなることも考えられます。
とはいっても、いますぐ繰り上げ返済をする必要はありません。金利は上昇傾向にあるという段階であり、今後必ず上がるとは限らないからです。
繰り上げ返済は思い立ったときに即日でできるので、金利が急激に上がり、繰り上げ返済をしないと損になる、または完済できないという状況になってから行っても遅くありません。
金利上昇を見越して早めに繰り上げ返済を行うと、現金が減ることによるデメリットやリスクの方が大きくなる恐れがあります。
例えば、子どもの進学を控えているタイミングで繰り上げ返済を行い、教育費に足りない分は学資ローンで借りるとします。一般的に住宅ローンよりも学資ローンの方が金利が高いので、かえって損をすることになります。繰り上げ返済は行わず、現金で教育費を用意した方が賢明です。

繰り上げ返済を検討するポイントは「政策金利の1%超え」
繰り上げ返済を検討するのは「急激に金利が上がったタイミング」。そうはいっても判断が難しいですよね。ポイントは、日銀が短期金利のターミナルレート(政策金利の引き上げによる最終到達点)としている「1%」です。
短期金利とは1年未満の貸付けに適用される金利のことで、変動金利に影響します。一方、長期金利は1年以上の貸付けに適用される金利で、固定金利に影響します。
現在は短期金利1%を目指して、半年スパンで0.25%ずつ上がっている状況です。このまま1%で収まっている状態が続くようなら、繰り上げ返済は行わなくてもいいといえます。
仮に日銀がターミナルレートを引き上げ、短期金利が1%を超えてくるようであれば、繰り上げ返済を検討した方がいい段階に入るでしょう。
短期金利の変動を予測するため、長期金利もチェックすることをおすすめします。現在の長期金利は、短期金利の上昇を見越して1.5%程度にとどまっています。現実に政策金利が1%を超えてくるとすれば、これを織り込んだ長期金利は1.5%を超えてさらに上がってくるでしょう。
2つの繰り上げ返済「期間短縮型」「返済額軽減型」
繰り上げ返済を行う際は、「期間短縮型」と「返済額軽減型」のいずれかを選択することになります。
「期間短縮型」はその後も月々の返済額は変えず、返済期間を短くするタイプ。「返済額軽減型」は返済期間を変えず、月々の返済額を減らすタイプのことです。
状況によって選ぶべきタイプは変わりますが、繰り上げ返済によって減った資金を、再び元の水準に戻していき老後に備えることを考えると、「返済額軽減型」を選択して月々の支出を抑え、貯蓄に回す方が現実的だと考えられます。
遺産相続などで思いがけず入ってきたお金を繰り上げ返済に充てる場合などは、手元の現金は減らないので、「期間短縮型」を選ぶという方法も考えられるでしょう。
- 本記事の内容は2025年4月掲載時の情報となります。情報が更新される場合もありますので、あらかじめご了承ください。

お話を聞いたのは●千日太郎さん
せんにち・たろう/公認会計士、オフィス千日合同会社代表社員。大学卒業後、大阪の監査法人へ入社。資格や名前を伏せて始めた「千日のブログ 家と住宅ローンのはてな?に答える」が評判を呼び、住宅ローン、不動産分野で人気の高いコラムニストとなる。YouTubeでは、公認会計士としての金融商品の分析力と独自のノウハウをもとに、日々寄せられる読者からの相談に的確なアドバイスを行う。著書に『住宅破産』(MdN新書)、『住宅ローンで「絶対に損したくない人」が読む本』(日本実業出版社)など。
https://sennich.hatenablog.com/