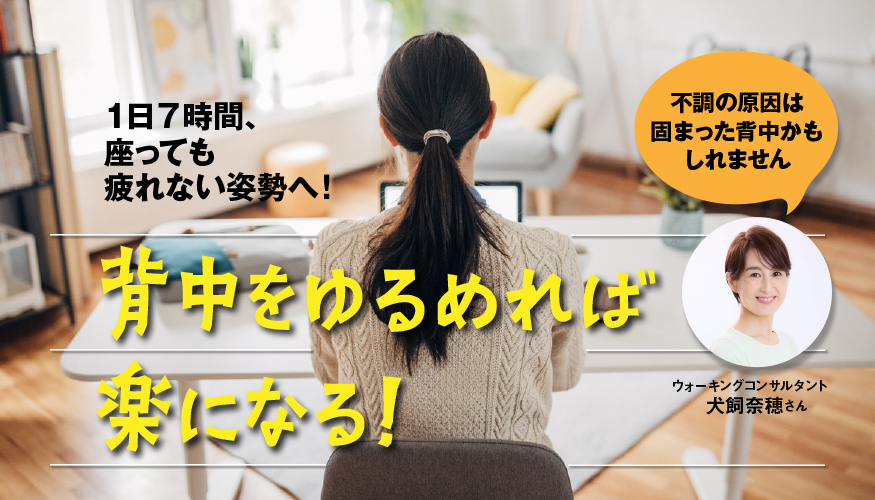キャンプや登山、非常食にもぴったり
ドライフードは食材を干したもので、いわゆる「乾物」のことです。水分を抜くことで食材が傷みにくくなるので、日本では昔から保存食として親しまれてきました。食材によっては1カ月以上の長期保存も可能になるので、自宅で余った野菜や果物を有効活用することができます。
さらに、太陽の光を浴びることで水分が抜けて、食材の持つビタミンがギュっと濃縮されて栄養価が高まり、うまみが濃くなります。日々の料理に使えるのはもちろん、そのままでもおいしく食べられます。漬物など火を使わないレシピも豊富なので、キャンプや登山、非常食にもぴったりです。
ドライフードには、完全に乾かさずほど良く水分を残した「セミドライ」と、完全に乾燥させた「ドライ」の2種類があります。セミドライは食材本来の味をよりおいしく味わうことができ、ドライは長期保存や持ち歩きに適しているため、好みや用途によって使い分けることができます。
簡単3ステップ! ドライフードの作り方
ドライフードのつくり方は、【切る】【並べる・吊るす】【干す】の3ステップです。
1.食材を切る
食材の水気をとって、適当な大きさに切ります。薄くスライスすれば水分が抜けやすくなるので、干す時間を短縮できます。
2.ざるやネットなどに並べる・吊るす
切った食材をざるやネットに並べたり、ピンチハンガーで吊るします。風に飛ばされやすい食材もあるので、ホームセンターなどに売っている野菜干し専用ネットを使うのもおすすめ。これを使えば、鳥や虫に食べられる心配もありません。
3.日当たりのいい場所に干す
日当たりと風通しの良い場所に干します。外に干せない場合は、日の当たる窓際でOK。時々ひっくり返して、まんべんなく太陽や風に当たるようにしましょう。干す時間は食材によってさまざまですが、セミドライの状態なら2~3時間から半日、ドライの状態なら数日から1週間程度で完成します。

湿気は大敵なので、天気予報には注意して、雨が降ってきたら室内に取り込みましょう。途中までしか乾いていない場合は、レンジやオーブンで仕上げることもできます。低いワット数や温度で、食材の様子を見ながら調整してください。
できあがったドライフードは、保存袋や保存容器などに入れて保管します。セミドライは水分を含んでいるので、生の食材と同じように冷蔵か冷凍で保存して早めに食べ切りましょう。ドライは常温保存できますが、水分が残っていたり、保存状態がよくないと痛んでしまうので注意が必要です。
おすすめの食材と使い方
初心者におすすめの食材は、キノコです。鉄板のしいたけはもちろん、マイタケは干すと香りが豊かになるので、炊き込みごはんにするととてもおいしいです。
キュウリも失敗しづらい食材の一つ。醤油やドレッシングで戻すだけで、簡単に漬物がつくれます。トマトはオリーブオイルに漬け込めば、セミドライは冷蔵で2週間、ドライは常温で1カ月ほど保存可能。パスタの具材やサラダのトッピングなど、さまざまな場面で大活躍します。大葉やショウガ、ミョウガなどの薬味類もストックしておくと便利に使えます。

私のお気に入りはレタスです。数時間天日干しにしたものをスープに入れるとグッとうまみが増し、レタスチャーハンにするとお店で食べるようなシャキシャキした食感を楽しめます。
果物が余っていれば、自家製のドライフルーツにも挑戦してみましょう。少し干すだけでも甘味が濃くなり、食感も変化します。そのまま食べればヘルシーなおやつに、ヨーグルトやアイスクリームとも相性バッチリです。
ドライフードを自作するのはハードルが高いと感じるかもしれませんが、コツを掴めば難しくありません。いろいろ試して、自分好みの干し加減や使いやすい食材の切り方を探すのも楽しいものです。空気が乾燥している秋・冬はドライフードが作りやすい季節なので、「野菜がちょっと余ったから干しておこう」「キノコが特売だったからドライフードにしてみよう」など、手軽に日常に取り入れてみてください。

お話を聞いたのは●三宅 香菜子さん
フードコーディネーター。2011年にキャンプユニットCAMMOCを設立。アウトドアやパーティーイベントでの料理提供、メニュー考案、ワークショップなどを手がける。CAMMOCの著書、『はじめてのドライフード』(山と溪谷社)に、レシピ・料理の担当として携わる。
https://cammoc.com/