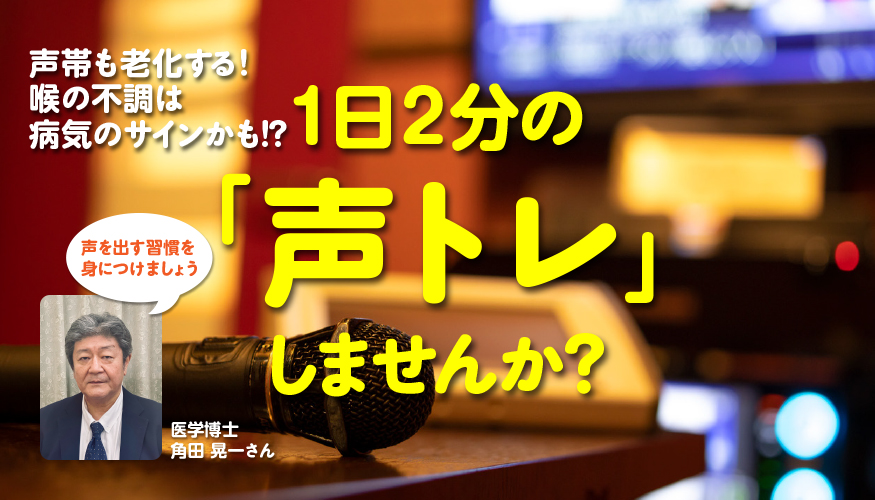サウナの最大のメリットは「脳疲労」が取れること
昨今のサウナブームでよく耳にする「ととのう」というワード。サウナの効果について、科学的なアプローチから解明する取り組みを行っている加藤医師は、サウナの効能・メリットについてこう話す。
「サウナは『気持ちいい』のはもちろんのこと、脳疲労を取ったり、睡眠の質の向上や美肌効果、自律神経の調整、冷え性の改善なども期待できます」
湯船につかるのと違うのは、温まった空気に頭まで全身を触れさせられる点だ。湯船よりもゆっくりだが、深部まで体が温まるという。
「深部体温が38度以上になると、ヒートショックプロテインという物質が出て、組織修復作用が働くほか、体が温まることで隅々の毛細血管にまで血流が循環し、冷え性の改善や美肌がかなうのです」
女性にはなんともうれしい話だが、サウナで得られる最大のメリットは「脳疲労が取れること」だと加藤医師は言う。
「人は、ぼーっとしている間にも絶えず思考をしており、体を休めても脳はなかなか休むことができません。そうした普段の脳回路が、サウナに入ると熱さで強制的に停止させられる。脳血流量も下がり、何かに熱中しているときの、雑念のない脳回路に自動的に切り替わります。それはちょうど瞑想と同じ状態。難しいテクニックもいらず、マインドフルネスを誰もが体験できてしまうわけです」
サウナ後は、脳疲労が取れ、集中力も増し、夜の睡眠の質も上がるという。サウナは基本、「サウナ→水風呂→休憩(外気浴)」で1セット。それらが体に与える強い刺激によって、自動的に副交感神経・交感神経に交互にスイッチングされる。回数をこなしていくと、自律神経が調整しやすい体になっていく。
さらには、サウナが心筋梗塞や認知症、精神疾患などの病気のリスクを低減するというエビデンスもあるという。

「ととのう」とは〝スッキリ〟しながら〝リラックス〟した状態
具体的に「ととのう」とは、どのような状態をいうのだろうか。
「サウナ後に水風呂に入ると、交感神経優位になって興奮物質が出ます。水風呂から出ると、今度は副交感神経優位になってリラックスしていく。でも、水風呂を出てから2分ぐらいは興奮物質がまだ体に残っている状態。普通はありえないのですが、わずかな時間だけ、頭がすっきり覚醒したまま、体はリラックス状態になる。これがいわゆる『ととのう』状態です」
加藤医師によると、ととのった状態の脳波を測定すると、覚醒度に関する脳波のデルタ波が下がっているという。デルタ波が下がると覚醒度は上がる相関関係にある。つまり、ととのった状態では覚醒度が上がることが科学的にも証明されている。
「水風呂の後のととのった状態で、そのまま横になってしばらく休むのがベストな休憩の仕方です。リラックスした体で横になると普通は眠くなりますが、ととのった状態では、眠気は少なく、頭や心はスッキリしているのが特徴です」
この休憩もまた非常に大切なステップなのだという。休憩せずにサウナと水風呂の繰り返し、といった極端な入り方で「ととのう」ことはない。加藤医師は警笛を鳴らす。
「水風呂の後はかならず、体が落ち着くまで、サウナに入っていた時間と同じくらい休憩をはさみましょう。休憩しないと、のぼせ症状や場合によっては、失神してしまうこともあり、非常に危険です」
サウナの回数や頻度は、体調次第で無理せずに
一度に3~4セットを繰り返すのが一般的なサウナの入り方とされるが、体調次第で無理をしないことを加藤医師は勧める。
「セットの回数や頻度、入浴時間はその日の体調によって加減して、固定しないほうがいいでしょう。入浴頻度もフィンランドの研究では、週10回以上は入りすぎで、女性は月経不順になりやすいというデータもあります。週2~7日までの範囲なら問題ないです」
入浴時間の目安として、加藤医師のお勧めは「心拍数」の計測だ。サウナでは、軽い運動程度の負荷がかかる。そのため、軽い運動程度の運動時の脈拍を計測しておき、それを目安にその脈拍に到達したらサウナからあがる。サウナ中の脈拍の計測は、好きな曲のBPM(1分間の拍数)などを指標にしてもいい。
「私の場合、心拍数120回が軽い運動程度になりますが、山下達郎の『クリスマス・イブ』だとBPM119回なので、あとちょっと。ウルフルズの『ガッツだぜ』になると、BPM124回なので、そろそろ水風呂に行こうか、となります」

飲酒後のサウナは危険! コロナ禍では黙浴を
サウナでの事故で多いのは高体温症だ。その9割は飲酒によるもの。飲酒後のサウナは厳禁だという。二日酔いでのサウナも脱水症状になりやすいので控えたほうがいい。サウナを出た後の飲酒も、先にたっぷり水分を補給してから飲むことが大切という。
「高血圧の持病がある方は、医師に相談してください。血圧コントロールができている状態であれば、まず問題ありません。むしろサウナは血圧を低下させる効果があります」
コロナ禍における入浴の注意事項は、通常の感染予防対策と同じだ。70℃のサウナであっても、ウイルスは5分程度、感染力を失わないとされている。人と距離をとり、おしゃべりを控えて、静かに過ごす黙浴がお勧めだ。
リフォーム&注文住宅で家用サウナをつくる
サウナの本場、フィンランドでは、人口約500万人に対し約300万のサウナがあるという。夜のサウナ後は暖かさが残っているので、暖かい木の部屋として利用され、そこでお酒を楽しむなど、文化として人々の生活に根づいている。
「近年、日本にもこのフィンランドのサウナストーブが入ってきています。サウナ室を作っておけば、サウナストーブを使って、家でサウナに入れますし、使わないときはリモートワークルームとしても活用できると思います」
サウナ人気で、日本でもいま、リフォームや注文住宅で家用サウナを設置する人も増加中だという。「サ活」をする女性も増えているが、加藤医師によると、実は、「ホルモンなどの関係で女性の方が本来、ととのいやすい」という。
「サウナ施設には行きづらい人でも、家にサウナがあれば、女性も習慣にしやすいはず。小さい子どもがいる家庭でも、子どもが寝てから夜中にゆっくり入ることができますから」
コロナ禍において、家用サウナ設置のメリットは無限大。正しく安全な入浴方法を守って、健康効果の高いサウナを楽しみたい。


お話を伺った人●加藤容崇 医師
かとう・やすたか/日本サウナ学会代表理事/慶應義塾大学医学部特任助教
1983年、群馬県生まれ。北海道大学医学部卒。専門はがん(膵臓がん)の遺伝子検査と研究。世界中の健康習慣を最新科学で解析することを第二の専門にする。サウナを科学し発信する「サウナ学会」を設立。著書に『医者が教えるサウナの教科書』(ダイヤモンド社)など。