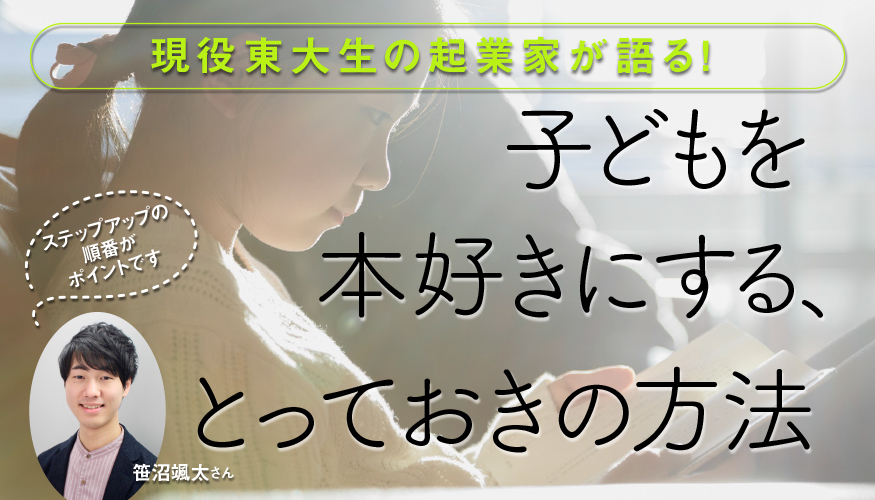本を読まない大人になると、人生の可能性が狭くなる!
昨今の子どもの読書離れの背景には、YouTubeやゲームといったインターネットコンテンツの普及が影響していると感じています。YouTubeやゲームが選べるようになったことで、わざわざ娯楽として本を選択する子が少なくなってしまったというわけです。
ただ、「読書離れ」といっても、読書が嫌いな子が増えているわけではないと思います。実際に、私たちが運営している「ヨンデミーオンライン」の会員にアンケートをとったところ、入会前からおよそ4割の子が、「元々読書が好きだった」と回答しました。読書は好きだけど、YouTubeの方がもっと好き。だから本を読んでいないのです。本を自主的に読んでいる子は、「元々読書がかなり好きだった」と回答した層だと考えられ、こちらはわずか1割でした。
では、なぜ子どもの読書離れは問題とされているのでしょうか。
私は、大人になった時に本を使って学ぶことができなくなるからだと考えています。私たちは学生ではなくなっても、さまざまな場面で学ばなければならない、もしくは学びたいと思う機会に直面します。もちろん、その時にYouTubeやWeb記事という手段を使って学ぶこともできるでしょう。ただ、こうした手段は、世界中の情報にすぐにアクセスできる、映像や音声がつくことでわかりやすいという利点がある一方で、情報が断片的にしか得られない、理解したつもりになりやすいという欠点もあります。
そのため、ある程度情報がまとまっていて、自分のペースで読み進むことのできる本が、一番学びの手段に適しているという場面もあるでしょう。しかし、子どもの頃に本を読んでいない人は、そもそも本を読むという選択肢がないのです。それって、本で学べる人に比べて、人生の可能性が狭まってしまうことになってしまい、すごくもったいないと思うんです。だから、子どもの時から本に慣れ親しんでおく、好きになっておくことが、とても重要だと私は考えています。

親ができるのは、本を好きになるきっかけづくり
子どもが本に慣れ親しむために、「ヨンデミーオンライン」では「楽しく・たくさん・幅広く」という言葉を掲げています。まずは本を読むことが楽しくなるように、楽しくなったら習慣化してたくさん読む、習慣化したら難しい本や違うジャンルにチャレンジ、と順を追ったステップアップが理想的だからです。この順番を変えるのは、絶対にNG。読書を好きになる前に本をたくさん読ませようとしたり、好きでもないジャンルの本を強制したりすると、子どもは読書を嫌いになってしまいます。
第一に目指すべきは、「この本面白い」「こういう本がもっと読みたい」と思えるお気に入りの本に出会うことです。ただ、そうした本にすぐに出会えるとは限らない。だから、家庭で本を楽しいから読みたいという気持ちを養い、本が読みたいと思った時に手に取りやすい環境を整えることが大切です。具体的な手段としては、読み聞かせをする、リビングに本棚を置くなどが、例として挙げられるでしょう。親自身が読書を楽しむ姿を見せるのも一つの手です。別に難しい本を無理に読む必要はなくて、子ども向けの絵本で十分。何だったら読んでいるフリだけでもいい。親が楽しそうに本を読んでいれば、子どもは自然と「読書って楽しいんだ」というイメージを持つでしょう。
お気に入りの本に出会うことができた後は、本が好きな気持ちを広げてあげましょう。その時にポイントとなるのが、「本を読んでいない時間」も本を好きになるチャンスになり得るということです。例えば、読んだ本について感想を共有する、感想文を書く。そういった時間も楽しいと感じることができれば、本が好きという気持ちは膨らむでしょう。こうした本を好きになるきっかけをたくさん作ってあげることが、親としてできることだと思います。
「つまらない」と感じさせない本の選び方
実際に「子どもが手に取れる場所に本を置いてみよう」と思った時に悩みがちなのが、「どんな本を選ぶべきか」ということです。本を選ぶ際に重要なポイントは、子どものレベルに合わせることだと私は考えています。なぜなら、子どもが「読書がつまらない」と感じる時は、大体難しすぎて理解できていない時だからです。
本を選ぶ時の一つの基準として、学校の推薦図書や書店の「◯年生におすすめの本」を参考にする人もいるでしょう。でも、人によって楽しめるレベルには差があるので、一概にそこに当てはめようとするのは危険です。小学4年生でも、絵本なら面白く感じるという子もいれば、分厚い小説も無理なく楽しめるという子もいる。特に、学校の推薦図書は少しレベルが高めに設定されていることが多いので要注意。一般的に年齢相応とされている本よりも、自分のレベルに合った本を楽しくたくさん読めることの方が重要です。
レベルの話で言うと、読み聞かせで理解できている本が、一人で読んで理解できるとは限らないということも、知っておいてほしいポイントです。なぜなら、読み聞かせであれば、読めない漢字があっても関係ないし、わからない言葉や展開があっても、親が教えてあげることができるからです。だから、読み聞かせで使っている本よりも、簡単な本を用意してあげる、もしくは少しずつ一人で読める範囲を増やしていくという工夫が必要です。
子どもに本を与える時、親はその本に対して期待しすぎないことも大切です。「せっかく読むなら、この本から何か学んでほしい」「こういう感想を持ってほしい」と、親は思ってしまいがち。でも、合わない本は必ず存在します。合わない本を無理に読み続けるくらいなら、途中でやめて別の好きな本を探す方が、読書に対してポジティブでいられます。10冊に1冊、刺さる本があればいい、それくらい気楽に構えておけると良いでしょう。そういう意味で言うと、図書館を利用するのがおすすめです。お金がかからないので、途中で読むのをやめることにも抵抗感が少ないからです。読書を通して成長する、何かを得るということよりも、大人になっても「読書ができる人間」を育てることに最も価値があり、一生の財産になる。それさえ忘れなければ、子どもが本を好きになる環境を整えることは難しくないと思います。
(2023年2月21日掲載)

お話を聞いたのは●笹沼颯太さん
ささぬま・そうた/株式会社Yondemy 代表取締役。現在、東京大学経済学部4年生。筑波大学附属駒場高等学校卒業。家庭教師をしていた時、読書について相談されたことをきっかけに、「子どもの読書離れ」について考えるようになる。英語多読講師としての読書指導ノウハウや、海外の読書教育実践に関する知見を活かし、2020年に日本初のオンライン読書教育サービス「ヨンデミーオンライン」を立ち上げた。
https://lp.yondemy.com/